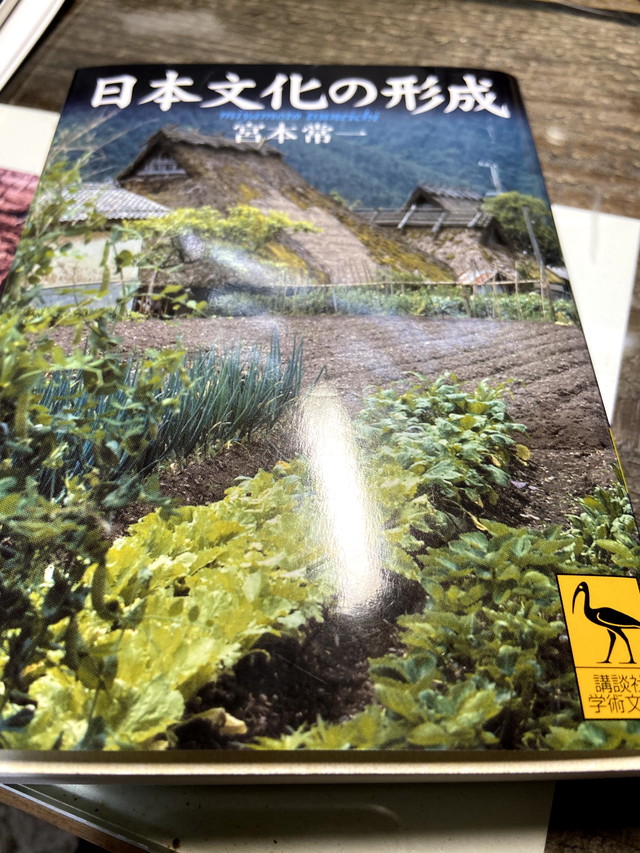「日本文化の形成」宮本常一
継続中の宮本常一シリーズ。その6。彼の遺作となった「日本文化の形成」
古事記、日本書紀、延喜式、、、などの古典や初めて聞くような数々の古文書を中心にして日本という国がどのように作られてきたかという観点で縄文時代から大和朝廷のころまでの流れを書いている。
この時代についての予備知識は他の時代と比べても少ない。そのせいか次々と初めての地名、国名、人名が登場し上の空で読み通した。そしてもう一度最初からゆっくりと読んでみたら少しは流れが理解できた。
彼の知識の豊富さには圧倒される。彼がこの本を書いたときと私の年齢はほぼ同じ。私の現在の知識とその差に愕然とする。彼のような方を博学強記と言うのでしょう。
読書ノートの一部
************
縄文時代 紀元前8000年~紀元前300年頃
人々は 漁労 狩猟
土器の使用 貝殻類を煮ていた 肉は焼いていた
北方ではシベリアから石器などが流入ー人口も北方が多かったー遺跡が多い
朝鮮半島とは陸続き?
北方、東日本に住んでいた人たちを「毛人(エミシ)」「エビス」と呼ぶ
後に「アイヌ」
南西諸島(種子島、屋久島)にも縄文遺跡がある
弥生時代 紀元前300年~紀元300年
倭人:東南アジア、中国の海岸地方から北上して朝鮮半島南部経由で西日本に渡来した人たち
朝鮮(百済)、西日本を植民地化していたーー倭国
稲作が中国南方から朝鮮経由で日本(北九州)に渡来
短粒米が乾田(水を抜くと乾いた土地になる水田)で作られた
当時の倭人は家族で船で生活し移動していた
西日本では大和朝廷が形成されつつあった
7世紀:唐が百済を攻めてここの権益を失った
畑作(焼畑、定畑)
狩猟、採取の延長としての焼畑
ここでは夏の間だけヒエを作った
焼畑から定畑に進行
秦人(はたびと、秦氏)が農耕技術を伝えた:日本全国に散らばって住んだ